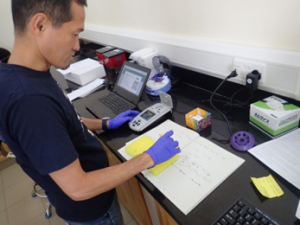2025年3月 家中茂さん 追悼
2025年3月 家中茂さん 追悼
3月20日 プロジェクトメンバーの家中茂さんがご逝去されました。
昨年のメイルのやり取りで病気療養中と伺ってはいましたが、突然のお知らせを受け、言葉を失いました。
長野大学から始まり、総合地球環境学研究所、愛媛大学のプロジェクトで共同研究者としてご協力いただきました。
本プロジェクトでは2022年マラウイ、屋久島、綾へ、またマラウイの研究者が日本滞在中には智頭に同行していただきました。
長くこの仕事をしていますといろんな研究者の方と出会います。
その中でも、常に情報に対して好奇心や探究心をお持ちで、新しいことに挑戦されようとする、博学多才な先生でした。
たくさん写真がある中から長野に一緒に出張した際の写真を掲載します。
家中先生、お世話になりました。楽しかったです、本当にありがとうございました。
-
2014年5月10日
長野県佐久市桜井地区にて 湧き水を味わう
-
2014年5月11日
長野県飯綱町サンクゼールにて いい笑顔
(文/写真 福嶋敦子)