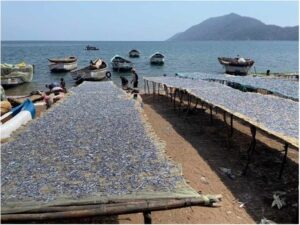2025年12月 マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也・佐藤哲
2025年12月 マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也・佐藤哲
マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也 12/1-15 佐藤哲 11/29-12/16
在マラウイ日本大使館、JICAマラウイ事務所、でプロジェクトの関する進捗状況の報告、また今後の打合せ、WOTA LTDにおいて小規模灌漑施設に関する打ち合わせと先進農家情報収集、Sustainable Cape Maclear農園調査、ZombaやBlantyreやLilongweの先進農家訪問、Nicholas Sikoya Chanza、 John Matewere、草苅康子らと研究打合せ、佐藤においてはChirundu潜水調査を行いました。
- チェンべ打合せ中
- 頑張れ70歳(佐藤 Chirundu潜水調査)
- Mantisさんと
- マラウイ大学周辺農場
- 広大なメイズ畑を通ってリロングウェへ移動
- リロングウェのスーパーマーケットにて流通に関する調査
- 番外1 Zathuでランチカンパンゴのフライ
- 番外2 村民手作りのランチョンマット 福嶋6枚お土産用に
- 番外3 とれたてのカンパンゴ この後、食す
- 番外4 マラウイ大学教員用の学食ヤギのシチュー